ここまで書いてきて、ふと、気づいた。ぼくはまだ、読者であるあなたに、「レイジーマン」という言葉についてちゃんと説明していなかった。というわけで、一度、話を過去へと戻したいと思う。スウェや仲間たちがレイジーマン・コーヒーを手がけることになったこの10年の物語の背後にある、100年の歴史にも思いを巡らせてみよう。
(文・辻 信一)
ジョニとの再会
ぼくが最初にノンタオ村を訪れて、ジョニやスウェに出会ったのは2016年のことだ。その前日、チェンマイで会ったカレン族の青年が、ぼくに彼が尊敬する村の長老の話をしてくれたのだが、「レイジー・マン(怠惰な男)」という奇妙な英語で呼ばれる長老の話を聞くうちに、ふと、ぼくの心に、長く埋もれていた記憶が蘇った。それはたしか、1996年のこと。屋久島で行われた「先住民の杜」という名の集いに出席したぼくは、たしかタイのカレン族だという男性が、木を守るためだといって、幹に黄色い布をかける儀礼をとり行うのを見た。なんでも、そうすることで、その木は神聖な存在となり、伐採から守られる、といった話だった・・・。
もともと物覚えの悪いぼくのたどたどしい話を無表情で聞いていた青年は、ちょっと間を置いてから、表情を和らげてからこう言った。「そう、それがレイジーマンです。彼はその方法で5千万本の木を守ったのです!」
そしてこうつけ加えた。「もう会っていたなら話が早い。さあ、ぼくたちの村にお連れします。行きましょう」

不思議な縁に導かれて、ぼくは翌日の夕方、迎えに来てくれた青年と、レイジーマンの娘だという若い女性に連れられて、ノンタオ村へ向かうことになった。そしてその夜、20年ぶりに、あの男、レイジーマンことジョニ・オドチャオに再会したのである。
チェンマイのパーティーでぼくが出会った青年の名はオシ、彼と一緒に迎えに来てくれた女性は九人いるジョニの子どもたちの末っ子ムポだった。
ただならぬ縁を感じたのは、まず、ジョニがぼくに挨拶も終わらないうちに、自分の名前の由来を話したときだ。彼が生まれた第二次世界大戦末期、敗走する日本兵が彼の村にも来ていた。彼の生家の軒下にも傷病兵たちが休んでいた。そんなときに生まれてきた赤ん坊の魂は日本からやってきたに違いないと考えた人々が、彼に「ジャパニ(日本人)」という名をつけた。でも、のちに、出生届の際に、役人が聞きちがえて「ジョニ」と記したらしい。彼は満面に笑みを浮かべながら、ぼくに言ったものだ。「だから、日本は私のもう一つの故郷なんだよ」。
もう一つぼくに深い縁を感じさせた出来事は、ジョニのうちに泊まった翌朝のことだ。階下に降りてきたぼくを芳醇なコーヒーの香りが迎えた。タイの山奥の少数民族の村で、誰がこの匂いを期待するだろう。台所で、ぼくのためにドリップでコーヒーをいれてくれているのがジョニの六番目の子で、当時30代後半のスウェだった。「コーヒーは好きですか?」と日本語で訊かれて驚いているぼくに、彼は自己流の英語と片言の日本語を駆使して、栃木県にあるアジア学院に留学して有機農業を学んでいたことがある、と説明してくれた。
コーヒーのうまさにも驚いた。なんとそれは、スウェ自身が栽培し、天日干しして、焙煎し、挽いたコーヒーだというではないか。口をぽかんと開けているぼくに、スウェはだめ押しの一品をもってきた。それはこの自家製コーヒーで小規模ビジネスを起こした彼が、焙煎した豆や粉を包装するのに使っているというパッケージだった。そこに貼ってラベルには、木の下に寝そべって、口をあんぐりと開けている男の絵。その上には英語で、「地球のためにスローダウンしよう」、その下には「レイジーマン・コーヒー」とあるではないか。
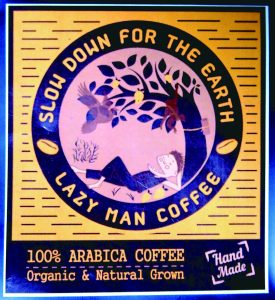
ぼくは短い滞在のうちに、レイジーマンその人に再会したばかりか、その家族や弟子に会い、レイジーマン・コーヒーと出会い、彼らが「レージーマン・ガーデン」とか、「レイジーマン・ファーム」とかと呼ぶ、田んぼや畑、森のような菜園などを見てしまった。ぼくの前に、レイジーマン・ワールドが開けた。
ノンタオ村への最初の訪問が、どれほど衝撃に満ちたものかをわかってもらうためには、まずぼくが、「レイジーマン」、つまり「なまけ者」などという変てこな言葉に、なんでそんなに反応するのかをわかってもらう必要がありそうだ。(ウィンドファームのお客さんなら知っていそうなものだけど、復習のつもりで)
スローな生き物 ナマケモノとの出会い
ぼくがナマケモノという動物に南米エクアドルで出会ったのは、今思えば、ジョニと最初に屋久島で会ったのと同じ1990年代の半ばだった。森林保護と、海岸のマングローブの植林の活動の中で、ぼくはこの動物に出会い、魅了された。今思っても不思議なくらい、ぼくはこの動物に夢中になって、未だ謎の多いその生態について学ぶために、中南米のあちこちを訪ねたり、資料を読みあさったりした。おかげで多くを教えられた。

ナマケモノの中でも、ミツユビ・ナマケモノは特に動きがスローだ。捕食者のうようよいる熱帯雨林で生きていくには、そののろさが大きな障害になりそうにみえる。しかし実は、動きが遅いのは筋肉が少ないからで、それはなるべくエネルギーを使わずに、葉っぱだけを食べて生きられるように進化した結果ともいえる。また筋肉が少ない分、体重が軽くなり、高木の上方の細い枝にもぶら下がることができ、それだけ天敵から襲われる心配も少ない。またナマケモノはいつも寝て暮らしていると言われるほど、動くことが少ないが、それも、動きを察知することに優れた猛獣や猛禽類から身を守るための知恵だともいえる。ぼくにとって特に衝撃的だったのは、ミツユビ・ナマケモノが、7、8日にいちど、危険を承知でゆっくりと木の根元まで降りてきて、地面にお尻で浅い穴を掘って糞をすることだ。こんなに動きの遅い動物にとって、地上は最も危険な場所だ。しかし、生物学者たちの研究によると、それはナマケモノが、自分に食べ物である葉っぱを供給してくれている木の根元に糞をすることで、もらった栄養をその木の根に確実に返そうとしている。つまり、自分を育ててくれる木々を、逆に支え、育てているというわけだ。これぞ、まさにエコロジカルで“持続可能”な生き方というものではないか。
こうして、ナマケモノとの“恋”は、ぼくの考え方や生き方に少なからぬ影響を与え、やがてぼくは仲間たちや学生たちと一緒に、ナマケモノ倶楽部というNGOを立ち上げ、ナマケモノをシンボルとするスローライフ運動を始めた。ナマケモノが住む森を守ろうというだけではなく、自分たち自身がナマケモノになって世界を変えようという運動だ。
さて、このナマケモノ倶楽部(通称ナマクラ)創設以来のぼくの相棒が、他でもないウィンドファーム代表の中村隆市なのだ。彼は、エクアドルはじめ中南米各地で、森を守りながら、森林農業によるコーヒー栽培を軸に、持続可能な暮らしを模索している現地住民たちを支援するフェアトレード運動を展開してきた。ウィンドファーム社のフェアトレードは、ビジネスと環境活動を見事に統合する先駆的なモデルだ。
そのウィンドファーム社がナマケモノ倶楽部と組んでつくりだしたのが、「森を守るナマケモノ・コーヒー」で、そのパッケージに貼られたラベルの写真は、ぼくがパナマで撮った野生のナマケモノだった。
気がつけば、ぼくとジョニ一家とは、ただならぬ縁でつながっているようだった。ぼくは、そしてたぶん彼らも、これから先の長く濃い友だちづき合いを予感し始めていた。
その予感通り、以後、ぼくは年に2、3度はノンタオ村を訪れてジョニ一家や村人たち、友人たちの話を聞くようになった。毎年、ぼくが大学で担当していたゼミをそこへ連れていって実習を行うようにもなった。「レイジーマン物語」というぼくが勝手に名づけた記録映像も撮り始めたが、その後4度にわたる撮影を経て、今ようやく完成の間際まできている。そして・・・。いやいや、先回りせずに、順を追って話していくことにしよう。
レイジーマン・ジョニとはいったい、何者なのだろう? そして、そもそも、レイジーマンとは何を意味するのだろう?
どん底の時代に学んだ 森の民、カレン族の生き方
レイジーマンことジョニ・オドチャオが生まれ育ったのは、タイのカレン族全体にとってどん底の時代だった。戦時末期の傷病兵たちがもたらしたといわれる疫病が蔓延していた。5人きょうだいのたった一人の生き残りであるジョニは、幼くして母と祖母を亡くした。家族は崩壊状態に陥り、幼いジョニは再婚した父のあとを追って、あちこちを転々としたという。また1920年代にこの地域にアヘンの原料となるケシ栽培がもち込まれて以来、カレンの多くは伝統的な森での暮らしと農耕を放棄し、てっとり早い現金収入を求めて、ケシ栽培を手がけ、自ら麻薬中毒に陥るという悪循環が進行した。強固な親族のネットワークを基盤とするカレン族の文化もまた急速に衰弱していた。ジョニの父も祖父も、他の多くの大人たちと同じように、アヘン中毒だったという。
早々と村を出て、水牛飼いなどとして働いた少年ジョニは、やがて村に戻ると、未だに伝統的な暮らしを続ける年寄りたちのところに身を寄せた。そして、森の民カレンの本来の生き方を一から学び始めたのだという。彼は特に神話、民話、伝承に惹かれたようで、物知りな長老を探し出しては、一人ずつ訪ねたという。二人の老人とのつき合いについてジョニはこう語ってくれた。
「ジョー叔父は長年木を植え続けていた。彼と一緒に住んで、私も木を植えることが好きになった。彼のやるとおりに植えた。村にはナーキエンという長老もいた。ナーキエンは私を誘って自分で守っている森を案内してくれた。それは彼が大切に守っている森林で、野生動物が豊富だった。鳥や野ネズミを捕まえて食べることもできた。その森はその後、ケシ栽培や木材伐採で破壊されてしまったけどね。私はそういう経験を通じて自分たちの森を守ろうと決心したんだ」
ジョニにせがまれるまま、何度も同じ話を繰り返すうち、物知りの年寄りたちはうれしそうに、「もうお前に教えることは何もなくなったよ」と言ったそうだ。文化の存続そのものが危うい状況の中で、しかし、ジョニはそうとは知らず、貴重な文化伝承者へと育っていった。
とはいえ、青年となったジョニは誰もがそうしているように村を離れては現金収入を得るためにさまざまな仕事をした。彼が二十代の半ばになる頃、インドシナ紛争を泥沼化させていた原因でもあった黄金の三角地帯の麻薬を一層するキャンペーンを国連が開始したのに合わせて、タイでも、ロイヤル・プロジェクトの名の下に農業近代化を進める一環として、北部タイのケシ栽培に代わる一連の換金作物の導入を図った。その代替作物の一つとして脚光を浴びたのがコーヒーであった。
結婚したジョニは、地域で始まったロイヤル・プロジェクトの先頭に立って働く勤勉な農夫となった。それまで飲んだこともないコーヒーの栽培も手がけたのもこの頃だ。当時彼が授与されたという、今は埃をかぶって蜘蛛の巣のはった額入りの賞状のいくつかを、ぼくも見せてもらった。ジョニはいわば、「緑の革命」と世界中でもち上げられた農業近代化のモデル農民となったのである。
だが、国連やロイヤル・プロジェクトによる支援には年数に限りがあり、新規に導入された作物への転換が、プロジェクト打ち切りのあとも継続的に成功した例は多くなかった。植えられたコーヒーの木のほとんどは、加工されぬまま放置されることになった。その当時、新しい換金作物を手がけるために融資を受けた者の中で、なんとか負債の淵から抜け出すことができたのは、私くらいだったよ、ジョニは言う。
模範的な農民だったはずのジョニのうちに、次第に疑念が膨らんでいった。そしてついに大きな転機が訪れる。時は70年代の終わり。
何かがおかしい。何年もジョニの中にわだかまっているものがあった。それが何であるのか、だんだん明らかになってきた。これは、自分の生きたい生き方ではない。これは、「パガニョー(タイ・カレン族の自称、人間の意)」の生き方ではない。国に勧められままに私が一生懸命やってきた農業は、要するに、畑で食べ物をではなく、お金をつくっている。それは、私があちこちでやってきた、雇われ仕事とどこが違うのか? 次々に村をあとにする若者たちが町の工場で働くのとどこが違うのか。
自分はまだいい。でも、ほとんどの村人が、いつまでも借金を抱えて、しまいには共同体を離れ、家族さえ失っていくではないか。借金で買った機械のためにパガニョーの最良の伴侶だった水牛を手放したり、農薬に頼って大地を汚し、水を汚したり、耕作地を増やすために、森を伐採したり・・・。こんなことをしていては、私は幸せではない。そして、誰も幸せにすることはできない・・・。
毎日、自由気ままに したいことだけを

こうして、ジョニの心の中に渦巻いていたモヤモヤとした思いは、ついに、はっきりとした像を結んだ。ジョニは、さまざまな農業のプロジェクトから手を引いた。といって、前のような賃労働を再開するわけでもない。毎日、自由気ままに自分のしたいことだけをして暮らすことにした。はじめのうち心配していた妻は、ジョニの変身が一時的なものではないと知るや、激怒した。私はこんななまけ者と一緒になったつもりはない! そしてこれは、その後長く続くことになる周囲の社会との軋轢の始まりでもあった。
このとき、すでにジョニの心のうちには、幼い頃から大好きだった民話のヒーロー、「ジョッカド」が蘇っていたのである。「ジョッカド」とは、パガニョー(タイ・カレン族)の言葉で「なまけ者」を意味する。これこそ、ジョニが「レイジーマン」と英語で呼ぶ、彼の英雄なのである。
「ジョッカド」の民話にはさまざまなバージョンがあるようだし、ジョニの語りも、その日によって異なる点がいろいろある。しかし、ストーリーの基本的な構造は同じだ。働くことより寝ることが好きで、のらりくらりと生きている若者が、しまいには、働き者たちより大きな成功を収めてしまう。この筋書きは、日本の民話にある「ものぐさ太郎」や「三年寝太郎」ともよく似ている。
ジョニはたいていこんなふうに語り始める。
「むかしむかし、あるところに
なまけ者のジョッカドが、おばあさんとくらしていました。
ジョッカドははたらきもせず、いつもぶらぶら、のらりくらり。
マコークの木が実をつけました。
友だちがジョッカドをそこへつれていきました。
でもジョッカドはその実をとろうともしないで
木の根もとにねころがって、口をあけました」
この、「木の根もとにねころがって口をあけ」ているジョッカドを描いているのが、レイジーマン・コーヒーのラベルにも使われている絵だ。そこから得たインスピレーションを糧に、ジョニは北部タイの農民運動のカリスマ的な存在へと変身を遂げ、スウェは、レイジーマン・コーヒを一つの柱とする新しい森林農業を確立していく。
自然を敬い、環境を大切にするジョッカドの教え
二人はジョッカドの物語から何を学びとり、それをどう、彼らの思想と行動に活かしてきたのだろう。
彼らによれば、ジョッカドの教えとは、まず第一に、謙虚であれ、ということだ。赤ん坊を見ればわかる。ただ口を開けて、食べ物が口に入るのを待つ。木の実が落ちてくるのを待つジョッカドのように。それなのに、いったいいつから人間は傲慢にも、実をたくさんつけるように木に要求したり、一人じめしたり、実が熟すのを待ちきれずにもぎとったりするようになったのだろう。

謙虚であれば、待つことができる。すべてのものには、それにふさわしい速さと遅さがあり、ペースがある。人間だって、幼子には幼子の、若者には若者の、老人には老人のスピードがある。それに抗うのではなく、それを受け入れる。これこそが、相手に対する思いやりであり、敬意というものだ。また謙虚であれば、人に批判されても、嫌われても、「なまけ者」とバカにされても、気にしない。いずれ、わかってくれる時が来る、と信じて待つことができる。
ジョッカド物語の教えとは、自然を敬う思想であり、環境を大切にする生き方−−今でいう持続可能な生き方−−だ。自然は惜しみなく与える。見返りを求めない。自然が求めるのは、ただ、その懐のうちで生きるものたちからの敬意だ。
タイ内外からジョニとスウェのもとへと遠路はるばる訪ねてくるものが後を絶たない。そんな人々に二人いつもこう繰り返している。「私もあなたも、みんな自然の一部なんですよ」
(文・辻 信一)

スウェさんとウインドファーム中村隆市代表
